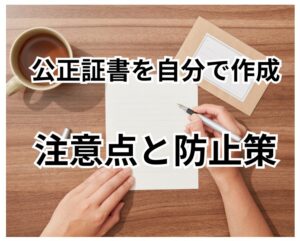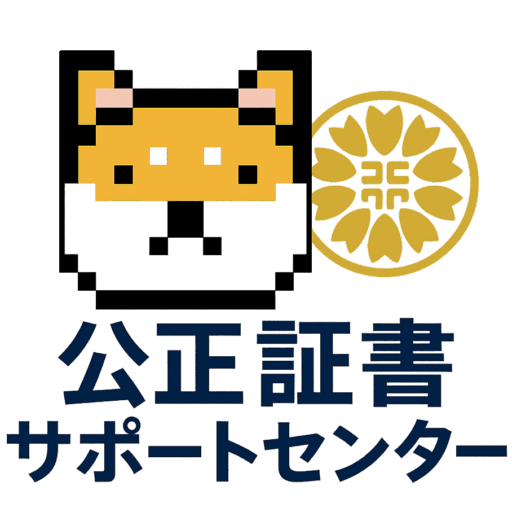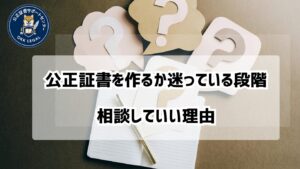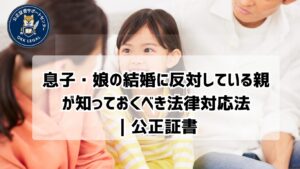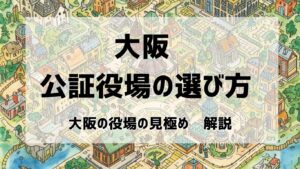目次
公正証書は絶対安心ではない
「公正証書=公証人が作成するから100%安心」と思われがちですが、実際には万能ではありません。
条件を満たさなければ無効になったり、効力が制限されたりするリスクがあります。
特に「公正証書を自分で作りたい」という方は気をつけながら作成が必要です。
- 無料相談や公証役場の窓口では、基本的な作り方の説明は受けられますが、実際にトラブル時に使える“実用的なライン”まではサポートされません。
- 公証人は公文書作成の専門家であっても、契約交渉や実務的なトラブル解決の専門家ではありません。
👉 本当に役立つ公正証書を作るには、公正証書の実務に精通した法律家の関与が不可欠です。
公正証書が無効になる代表的なケース
書類や手続きの不備
公正証書を自分で作る注意点
- 公証人の署名や押印漏れ
- 必要な添付資料(住民票・印鑑証明など)の不足
👉 書類や手続きの不備は、効力を根本から揺るがす大きな原因です。せっかく作成しても「不備があるため効力がない」と判断されれば、トラブル時に全く役立ちません。
公序良俗や法律違反の条項
- 法律で禁止されている契約内容を盛り込んでしまった
- 社会的に認められない取り決めを記載してしまった
- 作文になってしまってる
👉 このような内容を含むと、公正証書であっても「無効」とされる可能性があります。公証人のチェックが入っても、漏れがあればトラブル時に効力を失うリスクは残ります。
当事者の意思能力の欠如
- 認知症や未成年など、法的に有効な意思表示ができない状態の当事者がいる
👉 契約当事者に意思能力がなければ、その合意は無効となります。特に高齢者や未成年が関わる契約では、意思能力を証明するための工夫が必要になることもあります。
証人の不適格
- 利害関係のある人を証人にした
- 未成年を証人にしてしまった
👉 証人要件を満たしていないと、公正証書の作成自体が認められなかったり、効力に疑義が生じたりします。
強制執行条項の欠落
- 「支払います」とだけ書いて「強制執行認諾」の文言を入れ忘れた
👉 この場合、無効になるわけではありませんが、強制力が大きく下がります。
さらに、自分でで公正証書を作る場合、適用する条文の数や書き方によっても「差押え可能かどうか」の出来が変わってしまうため、実務経験のある専門家でなければ不安が残ります。
自分で作りたい人が気をつけるべきチェックリスト
「自分で公正証書を作りたい」という方のために、最低限のチェックポイントをまとめました。
- 書式を必ず公証役場のひな形に合わせる
- 証人は利害関係のない成年者を選ぶ
- 強制執行認諾の文言を必ず入れる
- 内容が法律や公序良俗に反していないか確認
- 本人確認・意思確認の手続きを省略しない
- 作文にならない
👉 これらをクリアすれば形式上は「公正証書」が作れます。
それでもリスクをゼロにできない理由
- 文言の細かい違いで「強制執行ができない」扱いになることがある
- 実務経験がなければ、気づけない落とし穴が多い
- 一度作って無効となれば、やり直し。手間も費用も時間もすべて無駄になる
👉 特に「支払いが止まったときに本当に使えるかどうか」が、公正証書の最大のポイント。そこが曖昧なら、公正証書を作る意味は半減してしまいます。
安心な作成なら専門家のサポートを
「できれば自分で公正証書を作りたい」という気持ちはとても理解できます。
しかし、トラブル時に確実に使える公正証書を作るためには、やはり専門家のサポートが不可欠です。
- 無効リスクを最小化できる
- 文案作成から公証役場とのやり取りまで一括で対応可能
- 当センターでは、大阪市全域に対応し、初回相談無料・24時間受付
まとめ
- 公正証書でも、要件を満たさなければ無効や効力制限のリスクがある
- 自作するなら最低限のチェックリストを守ることが必須
- ただし、それでも無効リスクを完全に排除することは難しい
- 大事な契約ほど「専門家に任せて確実に」作成するのが安心
👉 公正証書は「将来の安心」を担保する大切な書類。だからこそ、本当に役立つ形で残すために専門家へ相談するのがベストな選択です。
無料相談/24h受付⇩お問い合わせはこちら