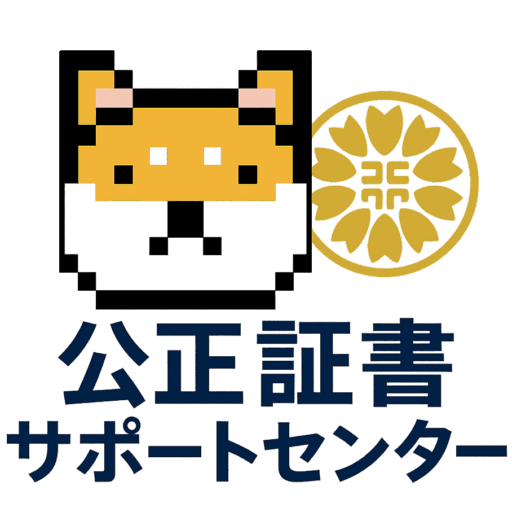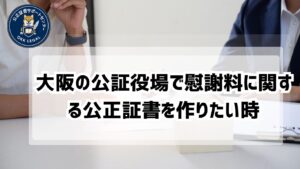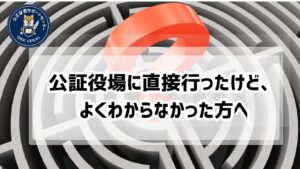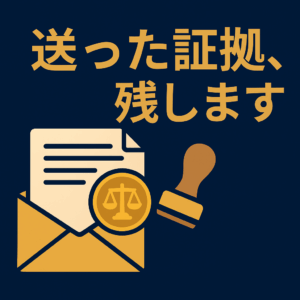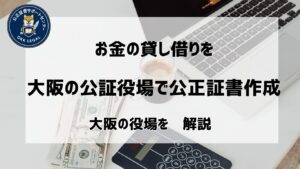事業融資の際に公正証書で保証人を立てる方必見|保証意思宣明で“安心して借りる”方法
「銀行から保証人を立ててくださいと言われた。家族や知人に頼めばいいのかな?」
ちょっと待ってください。
事業融資で第三者に個人保証をお願いする場合、2020年の民法改正により 『保証意思宣明公正証書(ほしょういしせんめいこうせいしょうしょ)』が必要です。
これを外すと、保証契約そのものが無効になる可能性があり、せっかくの融資がトラブルの火種になってしまいます。
この記事は、融資を受けたい側(社長・事業主)のための実務ガイド。
「いつ・誰が・何をすべきか」を、当センターの“やさしい断言”で整理します。
なぜ必要?──保証意思宣明公正証書の役割
個人保証は、重みを持つ厳しい契約です。
そのため、第三者が事業融資の保証人になるときは、公証人が内容とリスクを説明し、 本人が十分理解して同意していることを公正証書で宣明する仕組みが設けられました。
ポイント:宣明がなければ、保証契約は無効となるおそれ。 「保証人を付けたつもりが効かない」状態は、あなた(借り手)にとっても銀行にとっても最悪です。
誰に必要?──対象者の見極め
- 宣明が必要:社長の配偶者・親族・知人など、会社の役員ではない第三者が保証人になる場合
- 宣明が不要:代表取締役・取締役など、会社と経済的一体性がある立場の人が保証する場合
まずは誰が保証人になるのかを確定し、宣明の要否を判断しましょう。
いつやる?──“契約前1か月以内”が鉄則
保証意思宣明公正証書は、保証契約を結ぶ前1か月以内に作成します。
タイミングを外すとやり直しになるため、融資スケジュールに組み込むのがコツです。
どう進める?──最短でミスなく終える5ステップ
- 保証人候補の確定(第三者か役員かを判断)
- 必要書類・条件の整理(債務額・利率・返済方法・遅延時の取り扱いなど)
- 公証役場に予約(保証予定者本人が出頭)
- 宣明の実施(公証人が内容・リスクを説明し、本人が理解・同意を宣明)
- 1か月以内に保証契約を締結(必要に応じて契約自体も公正証書化)
実例:知人に保証を頼み、宣明を忘れたケース
大阪市のA社は1,000万円の運転資金を調達。銀行から追加保証人を求められ、社長の知人Bさんにお願いしました。
しかし宣明をしないまま保証契約へ。数年後に返済が遅れ、銀行がBさんへ請求したところ、Bさんは 「宣明がないので無効」と主張し紛争化。
結果、融資の継続や再編にも悪影響が出ました。
このケースは、宣明の取り直しと契約の作り直しで解決。
以後は「保証人が第三者なら、宣明→契約」の順番を徹底しています。
公正証書にしておく“+α”の安心(任意)
保証契約そのものを公正証書(執行認諾付き)にしておくと、滞納時の手続きがスムーズになり、 銀行側の安心感も高まります。
結果的に、融資プロセス全体が安定し、あなたの資金計画が崩れにくくなります。
よくある質問(融資を受けたい方向け)
代表取締役の私が保証人になる場合も宣明が必要?
不要です。代表取締役・取締役など役員は対象外。ただし、配偶者や知人など第三者が保証人になる場合は必須です。
宣明の内容はどれくらい厳しい?
公証人が債務額・範囲・リスクを説明し、保証人本人が理解・同意を宣明します。
「説明を聞かされる」のではなく、納得のうえで署名するための安全装置と捉えてください。
Q3. スケジュールがタイト。間に合わないときは?
スケジュールがタイト。間に合わないときは?
先に宣明を完了させ、1か月以内に保証契約を締結する段取りに切り替えます。
事前に当事務所が必要情報の整理・予約・書式を先回りで整え、遅延を防ぎます。
当事務所は 大阪府行政書士会に所属しています 。 公正証書の作成・相談は、あなたの街の法律家が対応します。
厚生省しよサポートセンター:トラブルを未然に防ぐ“設計チェック”
- 誰が保証人?(第三者=宣明必要、役員=不要)
- いつやる?(契約前1か月以内/融資スケジュールに組み込む)
- 何を確認?(債務額・期間・遅延時の扱い・情報提供義務 等)
- +α:契約自体の公正証書化で、安心とスピードを両立
「口約束を、守られる約束へ。」
今日の不安を、明日の安心へ。
宣明を押さえるだけで、融資はずっとスムーズに、ずっと安全に進みます。
▶ 事業融資で保証人を立てる前に、まずはご相談を
「宣明が必要か分からない」「日程がタイトで心配」「公証役場の段取りを任せたい」——
当事務所が最短ルートで段取りします。LINEで24時間受付中。