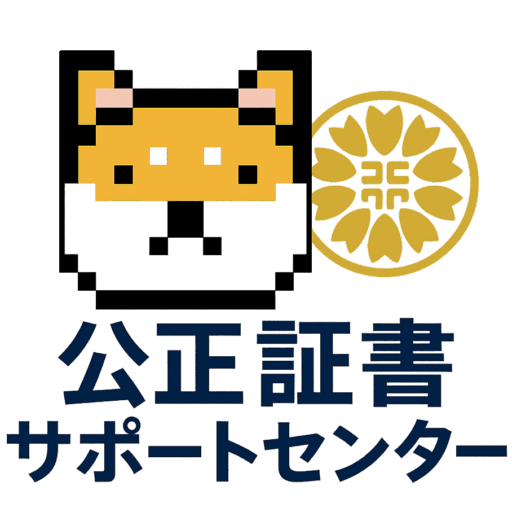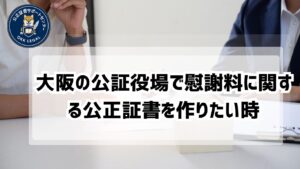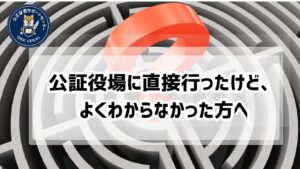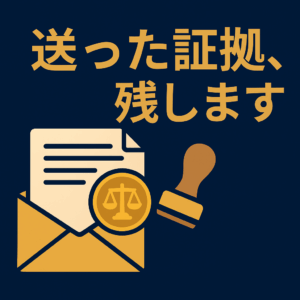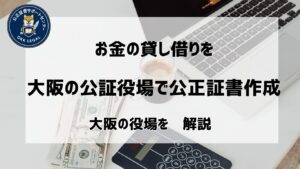目次
「借用書」は、良い一歩です。
身近な人にお金を貸すとき、
「あとで誤解が生まれないように」
「信用してるけど一応」と思い、
借用書を残すことは とても丁寧で誠実な判断 です。
借用書があることで、
- 貸した金額
- 返済期限
- 約束の内容
がはっきりと形に残ります。
まずここまでできている時点で、
問題の5割はクリアできていると言っても良いくらいです。
【借用書ひな型はこちら】
金銭消費貸借契約書
貸主 (以下「甲」という。)と借主 (以下「乙」という。)は、
下記の通り金銭消費貸借契約を締結する。
第1条(貸付金)
甲は乙に対し、金2,300,000円を貸し付けた。乙はこれを受領した。
第2条(返済方法)
乙は、令和 年 月 日までに、上記貸付金を甲指定の方法により全額を甲へ返済する。
第3条(利息)
本件貸付金について、利息は発生しないものとする。
第4条(遅延損害金)
乙が返済期日に返済しない場合、返済完了まで
年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。
第5条(協議事項)
本契約に定めのない事項が生じた場合、甲乙協議の上、
誠意をもって解決する。
6条(経過措置)
本契約、返済期日を遅延した場合公正証書等法的措置の直ちに協力する。
2項 費用は乙の返済金額に加えるものとする。
以上、本契約締結の証として、本書を2通作成し、甲乙署名押印の上、各自1通を保管する。
令和 年 月 日
甲(貸主)
住所:
氏名: 印
乙(借主)
住所:
氏名:
(連帯保証人)
氏名
住所 印
借用書は「約束を守るための土台」
借用書の役割は、
お互いの認識をそろえること。
人は、あとになればなるほど「言った」「言わない」の記憶がズレます。
だからこそ、文字にして残すことには大きな意味があります。
そのうえで、もう“ひとつだけ”用意しておくと安心です
借用書は「約束を残すもの」。
ただし
- 返済が遅れたとき
- 話しにくい状況になったとき
- 相手の生活状況が変わったとき
その時に、話し合いだけでは難しくなることがあるのも事実です。
これは借用書が悪いのではなく、
借用書の役割が “そこまで” だから。
ここで登場するのが、
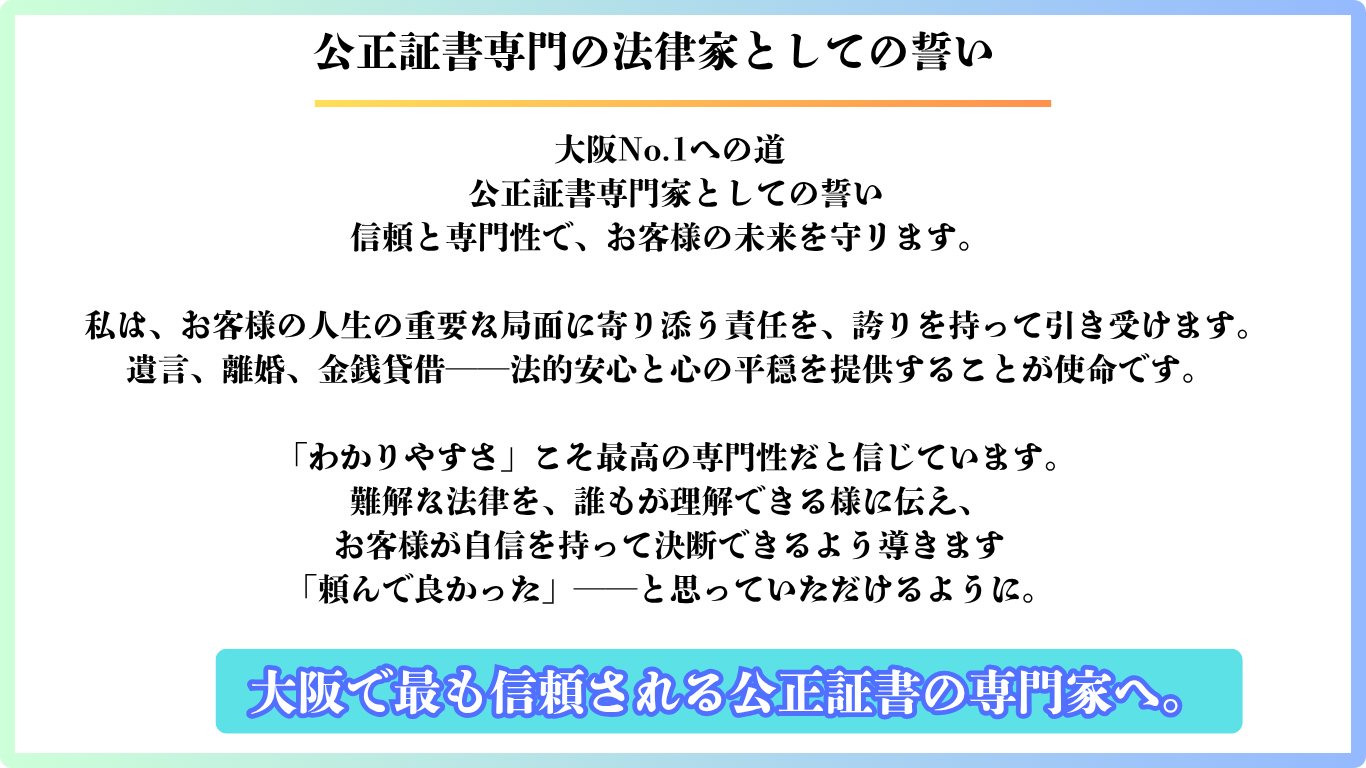
公正証書は「約束を国が保障」
公正証書には、
「もし返済が止まった場合に、給与や預貯金を差し押さえることができる力」
を付けることができます。
これにより、
| 借用書 | 公正証書 | |
|---|---|---|
| 約束を形にする | ○ | ○ |
| 誤解や認識のズレを防ぐ | ○ | ○ |
| 返済が止まった時に“動けるか” | △(話し合い→裁判) | ○(裁判なしで対応できる) |
となり、
借用書で整えた「約束」を、公正証書で“最後まで守れる状態”にします。
どちらが良い悪いではなく、
役割が違うだけです。
借用書がある人は、公正証書までの準備がほぼ整っています
実は、公正証書を作る際に必要なのは
- 金額
- 返済方法
- 返済期限
この3つ。
つまり、
借用書を書いた時点で、もうほとんどできている状態 です。
「いちから考え直す」必要はありません。
借用書 → 公正証書 は、
とても自然でスムーズな流れです。
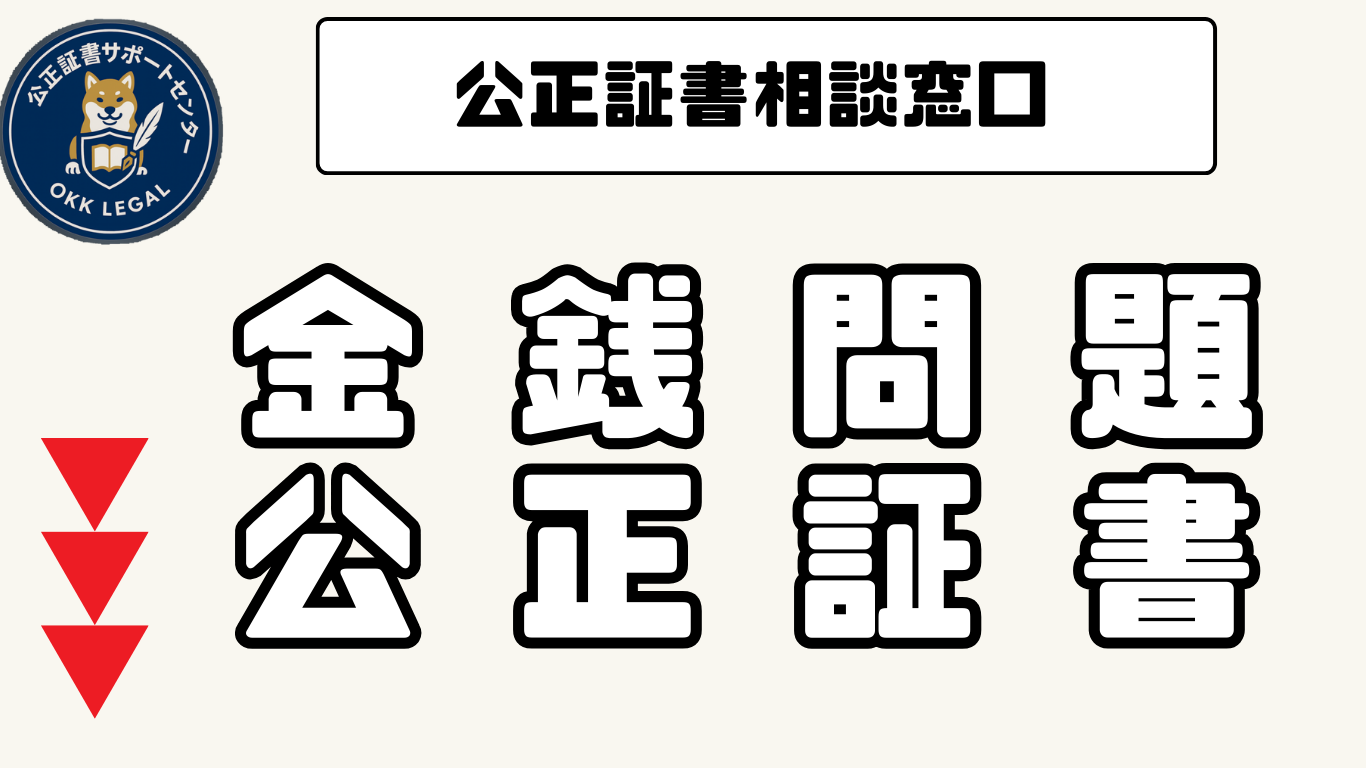
「相手を疑っているみたいで…」と感じる方へ
公正証書は、
相手への不信ではなく、関係を守るためのもの です。
お金の約束を曖昧にしたまま関係が崩れるより、
きちんと形にしておいたほうが、
お互いが安心していられます。
信頼しているからこそ、形にする。
これは、とてもやさしい選択です。
✅ まずは相談だけでも大丈夫です(来所不要)
- すでに借用書がある方
- これから借用書を書く方
- 相手に自然に提案したい方
状況に合わせて、最適な形をご提案します。
無理な契約・強引な誘導は一切していません。
大阪中心 / オンライン相談OK / 秘密厳守
不安を抱えたままにしなくて大丈夫です。
一度お話しすると、「今すべきこと」がはっきりします。


-作った物の公正証書化-300x169.jpg)