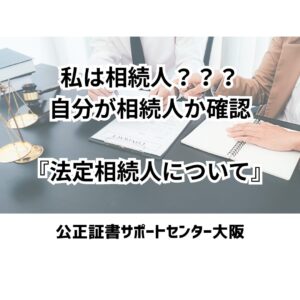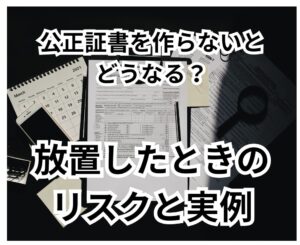多くの飼い主にとって、ペットは単なる動物ではなく“かけがえのない家族”。
そのため、飼い主に万一のことが起きた場合、 「誰が面倒を見るのか」「医療費や生活費はどうなるのか」 といった点が曖昧になり、最悪の場合、行き場を失ってしまうケースもあります。
こうした不安を解決する手段として注目されているのが「公正証書遺言でペットを守る仕組み」 です。
今回は、ペットの未来を安心して託すために、公正証書遺言をどのように活用できるのかを解説します。
ペットに遺言が必要な理由
ペットに財産は残せますか?
はい。もちろんあなたの意思を公正証書遺言としてペットの将来を守れます。
法律上「所有物」として定義ペット
民法上、ペットは「物」としての扱いになります。債権・物権といった各論で位置づけが整理されており、ペットその子に相続権が認められていません。
つまり、人間と違って「法定相続人」にはならないため、 相続財産の分け方を話し合う場でペットの存在は後回しにされがち なのです。
起きやすいトラブル例
- 親族がペットの引き取りが困難
- 遺産をめぐる争いのなかで、ペットの生活が軽視される
- 養育費や医療費が十分に確保されず将来のペットの生活が不安定
こうした事態を防ぐためには、 「誰に託すのか」「どのくらいの費用を残すのか」 をあらかじめ遺言で明記しておくことが重要です。
つまり、ペットにも人間の相続同様に「生活を守る仕組み」が必要なのです。
公正証書遺言でできること
公正証書遺言を活用すると、次のようなことが可能になります。
- 誰にペットを託すかを明確にできる
→ 公的効力を持つため、親族間の争いを避けやすい - 飼育費用・生活費を残すことができる
→ ペットのごはん代・医療費などを遺贈として指定できる - 遺言執行者を指定できる
→ 実際に内容を実行する人を決めることで、実際に執行者が動いてくれます。
「口約束」「普通の書面」では、法的効力が弱く、守られない可能性があります。
だからこそ、 公正証書遺言という“確実に守られる仕組み” を選ぶことが大切です。
公正証書遺言を使ったペットの守り方(具体例)
飼育を任せる人を指定+費用を遺す
例:「妹に愛犬を託し、生活費として300万円を遺す」
→ 引き受ける側も経済的負担が軽減され、安心して世話ができます。また、ペットのみの費用を指定することも可能です。
専門家に相談する
ペットを託す相手・費用・手続きの整合性を取るには、専門家のサポートが安心です。
当センターなら、ケースに応じた文案を提案してもらえます。
作成の流れ(ステップ)
- 誰に託すか、費用をどう残すかを考える
- 専門家に相談して文案を作成
- 公証役場で公正証書遺言として正式に作成
- 遺言執行者を指定して完成
👉 OKK 公正証書サポートセンターなら、文案作成〜公証役場調整までワンストップで対応。
初めての方でも迷わず進められる安心体制を整えています。
費用と期間
- 費用目安:基本料金8万円+公証人手数料(ケースにより変動あり)
- 期間目安:相談から完成まで約1〜2週間が一般的
- 初回相談無料:安心して第一歩を踏み出せます
まとめ:ペットも大切な“家族”だからこそ
ペットは法律上「所有物」として扱われますが、飼い主にとってはかけがえのない家族です。
だからこそ、万一のときに備えて「誰に託すか」「費用をどう残すか」を明確にすることが、ペットの幸せにつながります。
公正証書遺言は、ペットを守るための 最も確実で安心な方法。
大切な家族を未来につなぐために、まずは専門家へお気軽にご相談ください。



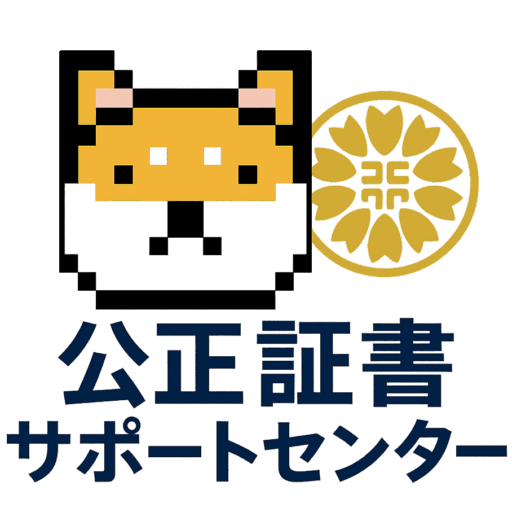
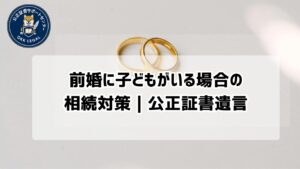
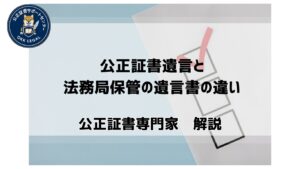


を含む場合の公正証書遺言|不動産の遺言を徹底解説-300x169.jpg)