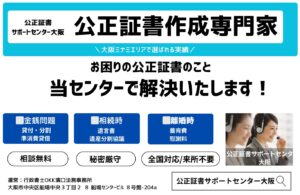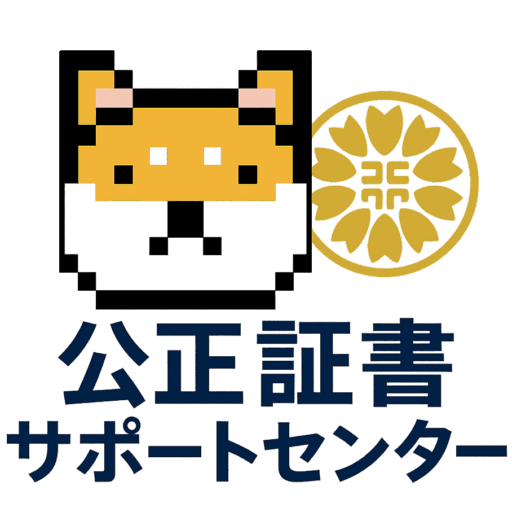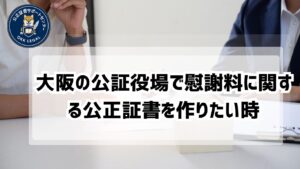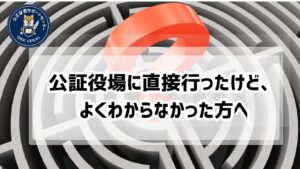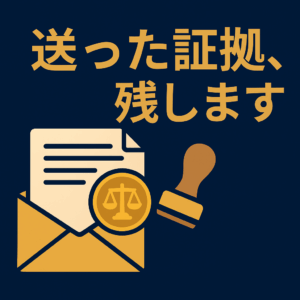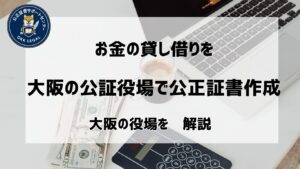中小企業が金融機関から融資を受けるとき、しばしば「個人保証人」が求められます。
経営者本人が保証する場合もあれば、親族や知人に保証を頼むケースもあります。
2020年の民法改正により、事業用の個人保証には「保証意思宣明公正証書」が必要になりました。
これを欠くと保証契約が無効になるリスクがあります。
この記事では、実際に「知人が保証人になったが、宣明をしていなかったケース」を紹介し、手続きの重要性を解説します。
個人保証は“軽い署名”ではない
事業融資の場面で「誰か保証人を立ててください」と言われるのは珍しくありません。
「信頼している人だから」「家族だから大丈夫」——そんな気持ちで署名をしてしまうことがあります。
しかし保証は借金と同じ重みを持ちます。しかも、保証意思宣明公正証書がなければ、保証契約は無効になる可能性があります。
知人を保証人にしたが宣明なし
大阪市で建設業を営むA社は、運転資金として1,000万円の融資を受けました。
銀行から「追加で保証人を立ててください」と言われ、社長は知人Bさんに頼んで保証人になってもらいました。
Bさんは「困っているなら助けたい」と署名・押印しましたが、保証意思宣明公正証書は作っていませんでした。
数年後、A社の返済が滞り、銀行はBさんに請求。
するとBさんは「保証意思宣明公正証書がないため、この保証契約は無効だ」と主張し、訴訟に発展しました。
宣明がなければ保証契約は無効リスク
民法465条の6により、事業用の債務を個人が保証する場合は、保証人本人が保証意思宣明公正証書を作成しなければなりません。
- 契約前1か月以内に作成する
- 保証人本人が公証役場へ出頭し、公証人が内容を説明
- 本人が理解・同意していることを宣明
この宣明がなければ、保証契約は無効になる可能性が高いのです。
結果として、貸主にとっては「保証人を立てたのに保証が効かない」、保証人にとっては「重い契約を十分理解せずにサインしてしまう」というリスクが生じます。
保証意思宣明公正証書を経て契約する
正しい流れは次のとおりです。
- 保証予定者が公証役場へ出頭
- 公証人が保証内容・金額・リスクを説明
- 本人が「理解・同意する」と宣明
- その内容を公正証書化
- 作成後1か月以内に保証契約を締結
これにより「保証人本人がきちんと理解した上で契約に参加した」ことが形式的に担保されます。
無効リスクを防ぎ、保証契約が揺らぐことはありません。
このような作業の、難しい面倒は全てお任せください!
有効な保証契約で双方が安心
後日、A社は知人Bさんに改めて宣明を経てもらい、保証契約を再締結しました。
その結果、次のような安心が得られました。
- 保証人:内容を理解して署名したので納得感がある
- 貸主(銀行):保証の無効リスクがなくなり、安心して融資できる
- 借主(A社):保証が有効であることが明確になり、取引先との信頼関係が維持できた
注意点:取締役や代表者は対象外
ここで誤解されがちなのが、経営者本人や取締役が保証人になる場合です。
この場合は保証意思宣明公正証書は不要です。
なぜなら、経営者や取締役は会社と経済的一体性があるため、改めて意思確認をする必要がないとされているからです。
つまり、保証意思宣明公正証書が必要なのは親族・知人など第三者が保証人になる場合です。
宣明を欠いた保証は“効かない”
事業用融資の個人保証は、従来の「署名・押印」だけでは不十分です。
保証人が第三者であれば保証意思宣明公正証書を作らなければなりません。
経営者が守るべきポイントは次の2つです。
- 保証人が第三者なら、必ず契約前1か月以内に宣明を行う
- 保証契約そのものは公正証書で作成すると、さらに安心
今日の不安を、明日の安心へ。
事業融資で個人保証を求められたら、必ず「保証意思宣明公正証書」を確認しましょう。
▶ 事業融資で保証人を頼まれた方へ
「保証意思宣明って何?」「誰が必要で、誰は不要なの?」
そんな疑問があれば、一人で悩まずご相談ください。
当事務所ではLINEで24時間相談受付しています。
法人の取締役の個人保証は?
会社の取締役や代表取締役
会社と「経済的一体性」があるとみなされる立場の人は、保証意思宣明を省略できるこれは「経営判断の延長だから、あえて意思確認は不要」とされているため。